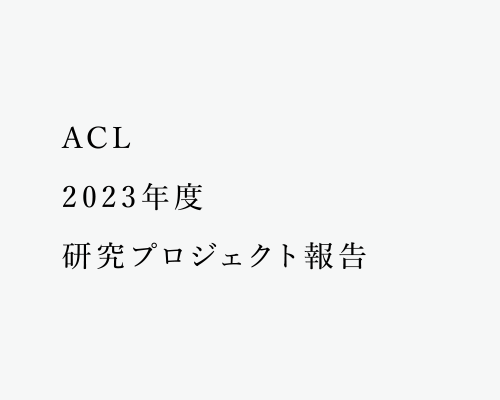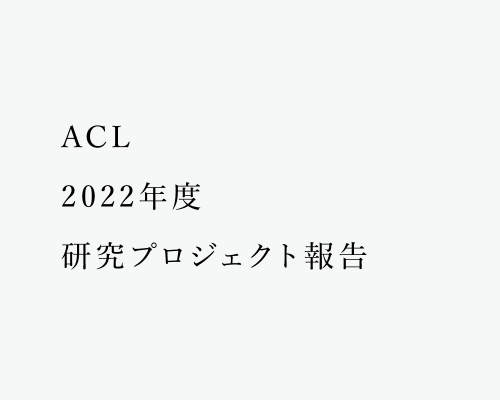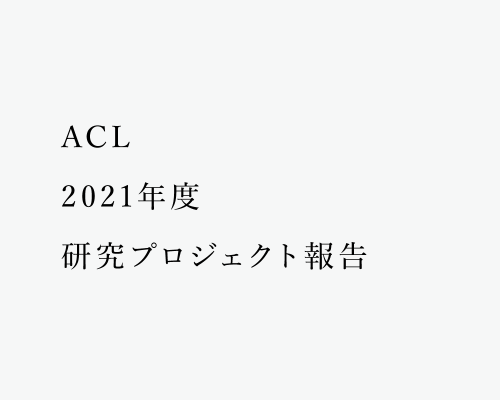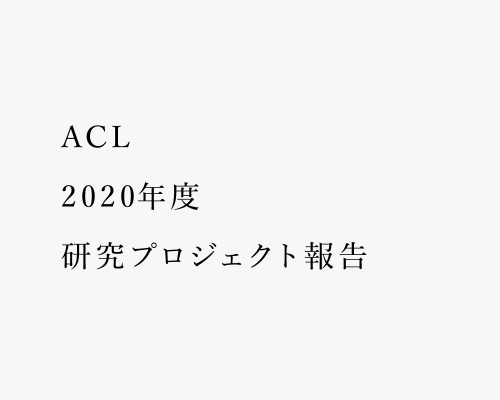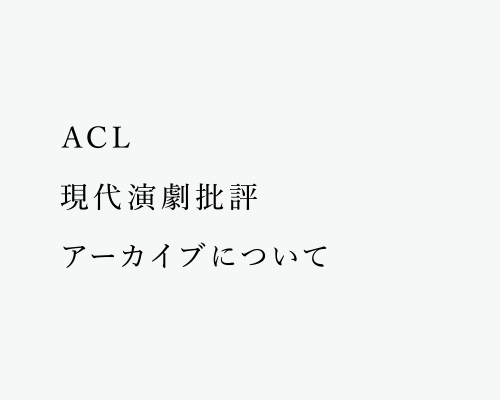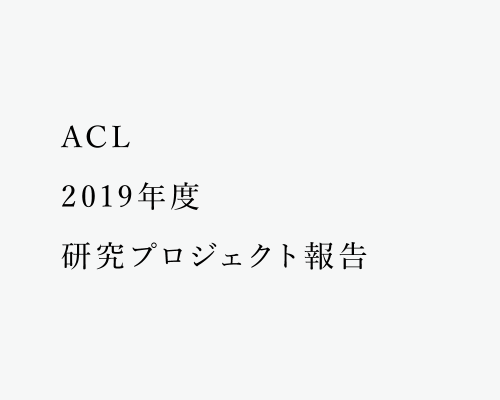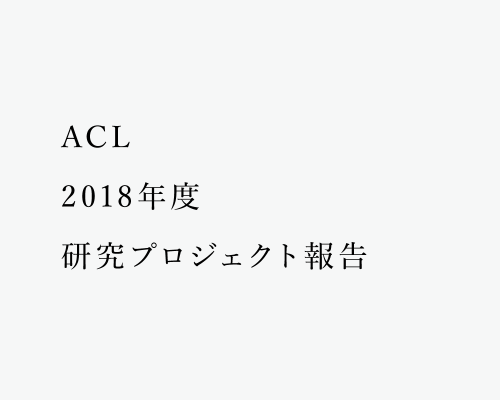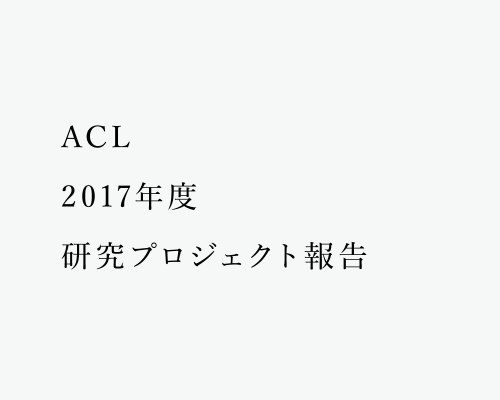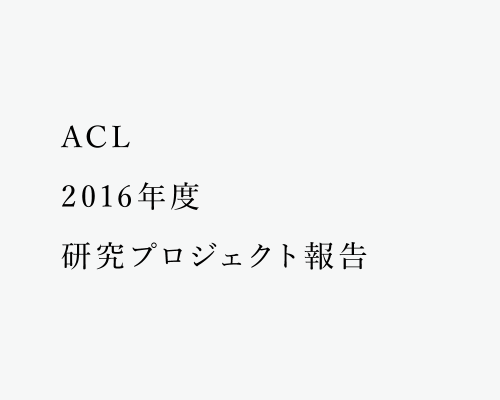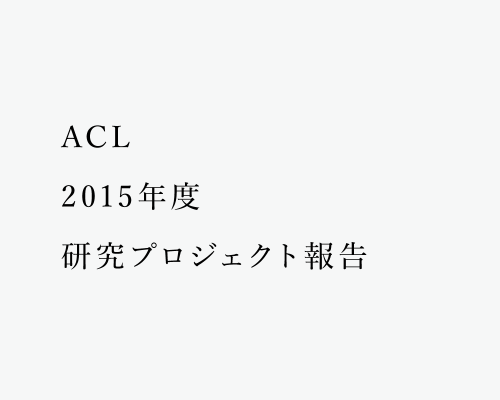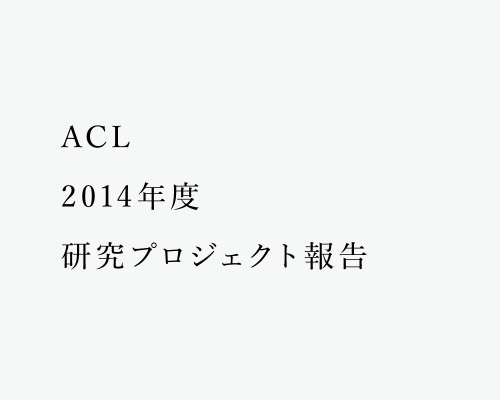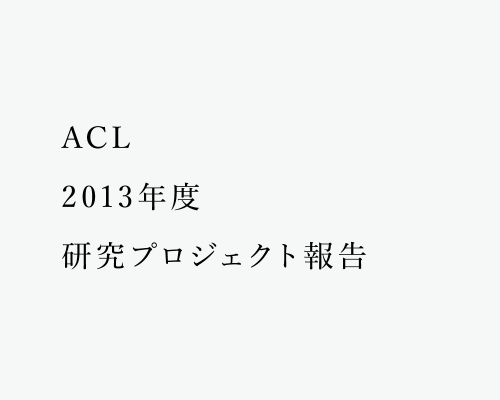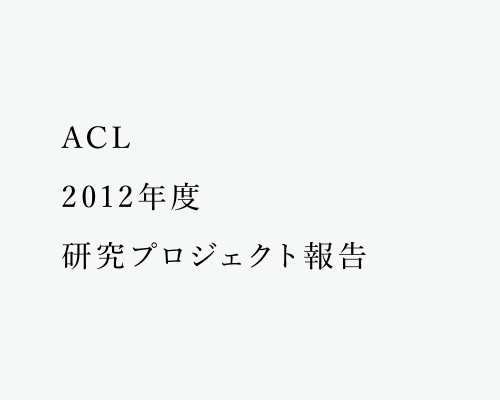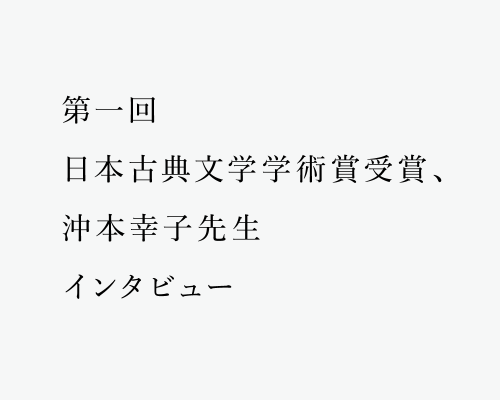- ARTICLE
- 第一回 石橋湛山新人賞受賞、伊藤真利子さんインタビュー(2)
- March.01.2021PRINT THIS PAGE
Part 2. 論文「郵便貯金の民営化と金融市場」について――伊藤真利子×杉浦勢之
杉浦:少し調子が上がってきたところで、受賞論文の内容を紹介してください。
伊藤:最近、郵政民営化の是非がニュースになっていますが、正確には郵政民営化は2段階で行われました。第1段階はもともと郵政省だったものが総務省を経て、2003年4月1日に日本郵政公社として公社化されたこと。第2段階は、郵政公社が2007年10月1日に4つの企業体に分割民営化されたこと。現在は100%政府の出資のもとにありますが、最終的には10年後の2017年までに、株式会社として完全民営化していくことになっています。
受賞論文では、公社化と4分社民営化の段階を踏まえ、主に90年代バブル崩壊以後の郵便貯金の動向を中心に、日本郵政公社がどのような問題を抱えていたのかということを、郵便貯金と金融市場の関わりから分析を行いました。
杉浦:大変アップ・トゥ・デートなテーマですよね。とかくセンセーショナルに扱われることが多い中で、論点を金融に絞ったというのは意外感があったのではないですか。
伊藤:郵政民営化は、2001年4月に発足した小泉政権により、「聖域なき構造改革」の本丸として取り上げられ、一気に進められました。その政策的眼目は、利益誘導型政治を通じた地方への所得再配分機構としての財政投融資の解体、特に道路公団の民営化とその資金源泉であった郵便貯金を民営化することにありました。いわば、政治的な意図の大変強いものだったのは事実です。ただ、ご存じのように金融というのは、それだけでは済みません。
郵便貯金は、2001年に財政投融資と切り離され、自主運用されるようになりましたが、郵貯資金の大半は、実は安全資産である国債を中心に運用されていたのです。日本郵政公社としては、こうした国債に依存した運用による大量保有では、民営化を進めることは難しかったわけで、そういった構造からの脱却が試みられました。
一方で、「失われた10年」と言われる1990年代の長期不況を通じて景気対策が行われ、大量の国債が発行されるという状況が続いていたわけです。長期不況の中ではゼロ金利政策で低金利におさえられていましたが、景気が回復し始めますと、金利が上昇しはじめ、国債価格が低落する懸念が表面化しました。大量の国債を保有している日本郵政公社にとっては経営的に非常に厳しくなります。民営化されれば、政府の考えとは別に、価格リスクの高い国債を大量放出することも考えられるわけです。そうなれば、国債価格が暴落し、金利が跳ね上がるなど、景気回復のシナリオが一気に腰折れしかねなかった。このため、民営化が政治的に推し進められるなかで、郵貯の存在は、国債市場を通じ、マクロ経済全体の大きなリスク要因になっていたわけです。この点を中心に論文をまとめました。
杉浦:構造改革路線が、長期不況を脱することを一つの課題としながら、その一環である郵政民営化によって、景気回復を脅かされることにもなったというのは、ある意味皮肉だと思うのだけれど、そういう問題というのは、民営化のセンセーショナルな議論に隠れて、一般に見えにくかったところですよね。その辺に着眼したというのが、今回評価されたのだと思うのだけれど、流動的で大変不透明な環境にあるこの時期に、あえて郵貯民営化を扱おうと思ったのはどうしてですか? 普通院生はリスクが大きすぎて、こんなテーマはやらないでしょう。
伊藤:修士論文のときから、「公と私」、「官と民」をテーマに、日本的な「公共性」について、実証的な研究をしてきていました。日本では、時代が変わっていく中、公私、官民という区分が交差しながら、公というものの担っているものが変化していくのですね。
郵政民営化は、明治期より官営企業であった郵政事業が段階を踏んで民営化し、民間企業となるということですから、公社化され、さらに民営化していく中で、事業性・企業性と郵政事業が担ってきた公的な使命、パブリックな使命とが、どのように折合いをつけていくのか、そこからもう一度日本の公共性というものをきちんと捉え直したいと思っていましたので、あまり研究の上でのリスクみたいなことは考えていなかったです。
杉浦:なるほど。いままさに問い直しが求められようとしているところですものね。論文を作っていく過程や研究の進め方はどのようなものだったのですか?
伊藤:きっかけのひとつは、「日本郵政公社史」編纂のプロジェクトでした。執筆される先生方のお手伝いということで生田正治元総裁をはじめ、郵政公社の方々のヒヤリングに参加し、郵政資料館での史料調査から一次資料にアクセスする機会をいただきました。それまでは教育経済史の論文を文献やデータ中心で書いていたのですが、今回の論文では、当事者の方々の肉声や膨大な一次資料を前にして、これは本当に正面から取組むべきだな、と。それはやはり全然違う体験でした。
杉浦:これまでの研究と違って、今回は現実との出会いが先にあったというか、現にあるものと格闘する中から、答えを探っていったということですね。ヒヤリングやフィールドワークというのは、伊藤さんにとっては初めての経験だったわけですが、論文とは別に、自身の体験として、どんなことを感じたのかというところを教えてください。
伊藤:そうですね、ヒヤリングを通じ、お話しを聞かせていただいた方々のエネルギーとか、伝えたい強い想い、ご苦労話などを自分なりに残していきたいと思いました。不遜ながら感謝の気持ちを表したいと思ったんですね。それでは、どういった形で残していけるのだろうとずっと考えていました。私は大学院生ですから、やはり論文という表現形態しかないと思ったのです。そこで、当事者であるがゆえに、郵政公社の方々でももしかしたら気が付いていないかもしれないことがある、外部者であるからこそ持てる視点といったものを活かしながら、そういった構造的な部分を何とか浮き上がらせることができないか。そして、郵政事業を日本の公共性という大きな枠組みの中で、もう一度きちんと検証していくことが、そういう真剣に生きておられる人々の営みに対する私なりのお答えになるのではないかということは考えていたように思います。
杉浦:当事者なるがゆえに見えない部分をきちんと見ていくというのは、確かにアカデミズムの役割でしょうが、それって結構しんどいんですよ、客観性を保ちつつ、当事者と同じ目線で対象にコミットメントしていくというのは。
伊藤:そう思いました。
杉浦:そういう意味で、今回の論文を支えた、伊藤さんにとっての本当の核になったものって、いったい何だったのでしょう?
伊藤:正直なところ、この変化の激しい世の中で、たった1人で、約26万人という日本一、いえ、おそらく世界一大きな組織体を引っ張っていかれた生田元総裁の情熱、そしてそれを支えたバックボーンのようなものに惹かれました。
生田元総裁は、健康に大変不安がおありだったにもかかわらず、小泉元首相の三顧の礼を断りきれず、総裁を引き受けられたという経緯があるのです。商船三井から、たったお一人で郵政という組織に飛び込んでいかれた。文字通り、お一人で公社に見えて、受付で「生田です」と仰ったそうです(笑)。
杉浦:それは凄いですね。だいたい側近を連れて、というのが普通なので。
伊藤:それから総裁就任決定を受けて、まず全国の郵便局、特に過疎地の郵便局を巡回されたそうです。そこで、地方の生活を維持するために必要なユニバーサルサービスという問題と直面したそうです。現場を目で見て確かめられることなしに、経営の改革はできないということだったのでしょうか。
杉浦:うーん。トップとして現場を肌で感じるというのは、絶対必要なことですが、政治の論理と企業の論理というのが非常に難しい状況にあったわけですから、下手するとこれまでのしがらみに絡めとられかねないということもあったでしょう。大変な決断というか、賭けだったでしょうね。生田さんは郵政の新しい仕組みや、経営カルチャーを作ろうとしたのだと思うのですが、一方で、郵政の社会的役割ということも求められるという難しい立場ですよね。ここは、伊藤さんの今回のテーマに重なるところですが。身内の問題だけでは済まない。そういう意味で、伊藤論文のコアになるテーマは、生き方において魅力的な組織人としてのありようと、そういった個人ではどうにもならない歴史的、社会的に背負わされた役割とのせめぎ合いということになるのでしょうね。
ところで、今に至るまで非常に気になるところなのですが、小泉元首相については、伊藤さんどのように捉えていますか?
伊藤:小泉元首相は当時、ワンフレーズ・ポリティクスなどとも評されましたが、国民の高い支持率を約2年維持し、政治に無関心だった国民を選挙にひっぱりだしたということは事実ですよね。小泉元首相の「言葉」が、あの時代を動かし得たというのは、やはり否定しがたいところですから、それがなぜなのかというのは、当時からずっと考えていました。
杉浦:実はこの前の沖本幸子先生との対談の際に、唐突に聞こえるかもしれないけれど小泉元首相のことを思い出していたんですよ。テーマは、古代芸能の「今様」についてだったのですが、平安時代から鎌倉時代にかかるところで、急に「肉声」ということが重要な意味を持ち始めるんです。詳しくはそちらに譲りますが、歴史的なシステムの変革期に、「個体性」というか、「身体性」というものが急激にせり上がってくる。それまで支配層というのは、「声」とか、そういう肉体をイメージするものを極端に忌避していたのが、後白河院になって、「声」によって民衆のパワーを吸収しようとするようになるんだそうです。後白河院の身体が歴史の中で異様に露わになるんですね。沖本先生の研究では、そういう危機の時代というか、特別な時代を、「今様」という芸能を通じて見事に浮き彫りにされています。そこでは「声」というものが過剰に意識されることに注目されているのです。むろん芸能史の文脈からのアプローチなんですが、政治史的文脈から読み替えが可能かもしれない、と。
おもしろいなと思ったのは、小泉政治も基本的には「声」。文字にしたらあまり内容がないというか、全然論理的でない(笑)。小泉劇場と言われたでしょう? 自民党がコントロールできなくなってしまった時、裂け目が生じた言説の場に、小泉元首相がメディアを通じて「総理の肉声」を与えたというか、あるリズムを与えたのかなとね。言葉の政治というのか、このままではいられないというリズム感でしょうかね。だからその後の政治家たちは、完全に「声」、言葉のところでリズムを崩されてしまっている。このままではちょっと建て直しができそうにない感じです。不可逆的な過程に一気に日本の社会が突っ走った気がします。しかし一方で当時、約26万人を抱え、355兆円もの膨大な資金を抱える郵政というのは、言葉だけでは動かしえないわけです。あるいは動かしたら、予想を超えるとんでもない影響が出てくるかもしれない。そこは小泉さんではあまり考えられてなかったのではないですかね。とてつもない改革を一気にやってしまったなと思いますね。
伊藤:時代の綻びに、ヒビを入れたのは小泉元首相でしょうね。確かに巨額な郵貯資金については危なくて動かしえなかったかもしれません。竹中平蔵さんは、そのことに気づいていたと思います。むしろそこが焦点だったのではないでしょうか。小泉元首相にしても、竹中さんにしても、結果をまったく恐れていない感じがします。それに対して、生田元総裁は、ご自身の経験と勘で、日本郵政公社という巨大組織の内部の人たちを確実に動かしたように思います。新自由主義者であると明言されながらも、規制緩和を通じて、雇用と生活を守ることのできる強い組織を構築するということを大変意識された。海運業界というのは、トップの責任感、従業員の一体感がとても強い業界ですから、おそらく、生田元総裁はそういった部分の良いところを郵政に持ち込まれようとしたのではないでしょうか。もっとも、新しい組織文化としての仕組みを整え、郵政の長い歴史と固陋な伝統の中に根づく前に、更迭されてしまったわけですけど。
杉浦:なるほど。短い期間であったとはいえ、新しい経営文化が生まれつつあったということですね。商船三井と郵政という異なる組織DNAが一瞬交わったのでしょうね。それがどうなっていくのか……今本当に迷路に入りこんでしまっていますが、そこはどうですか?
伊藤:様々なパワーバランスがあって状況が変わっていくと思うのです……。実際は目に見えない力が一瞬働いて、新たな公共性の線引きがある一定期間固定されるのかもしれないとは思っています。
杉浦:伊藤さんの口からは、言いにくいかもしれないですね(笑)。日本郵政の人々にとって、生田さんのなそうとしたことは「公」ですよね、つまり、会社という「公」があってそれをなんとかしなくてはいけないという。それに真っ向立ち向かった。ところが日本郵政公社は民営化されるということで、国から見たら「民」であり、「私」でなければならないですね。一方日本郵政が所有している財産は、もともとは全て国民の税金です。さらにその資金の運用は、国民経済に甚大な影響を与えます。そういう意味で、公共空間が、実はものすごく複雑なクラインの面をなしている。郵政民営化というのは、そういうことを全部露わにしたというか、そういったテーマに、伊藤さんが取り組まれたというのは、確かにこれまでの研究の延長上ではあったのだと思うのですが、でもやっぱり本当のところ生田さんの生きざまに惚れ込んで論文を書きあげたというのがありますよね。たまたま書けそうなものがあったから書いてみたというものじゃない。
伊藤:はい、あります(笑)。そここそがポイントです。人それぞれだとは思いますが、私の場合、惚れ込まなきゃ論文書けません。
杉浦:正直ですね(笑)。