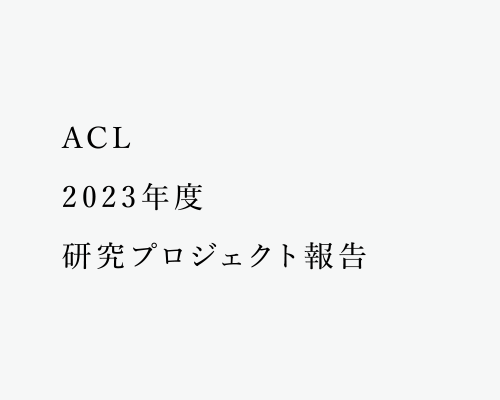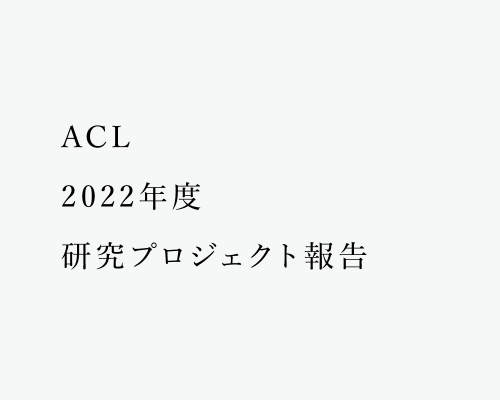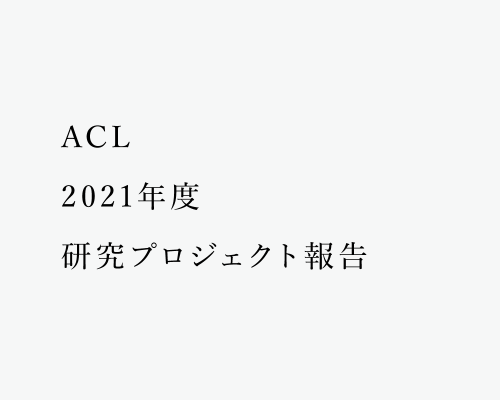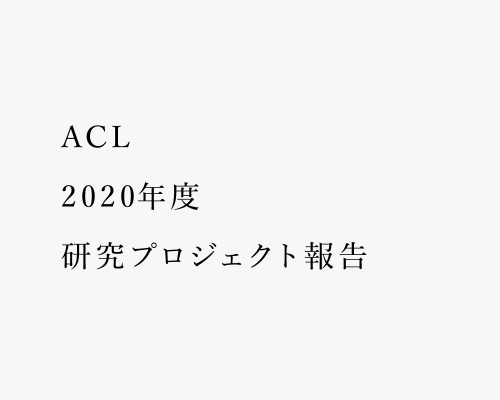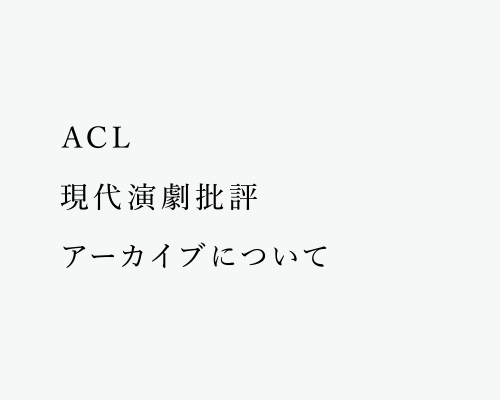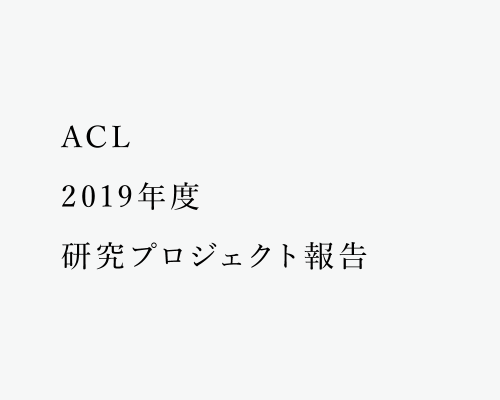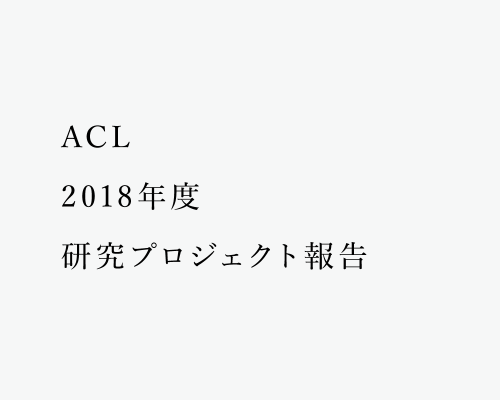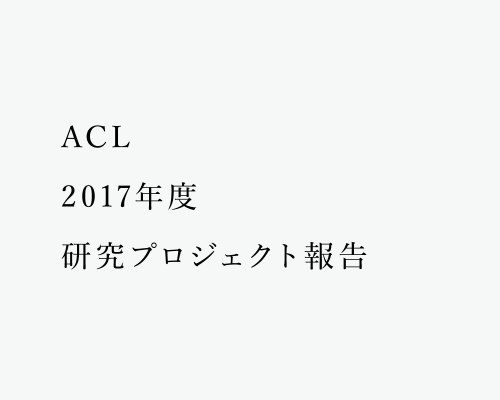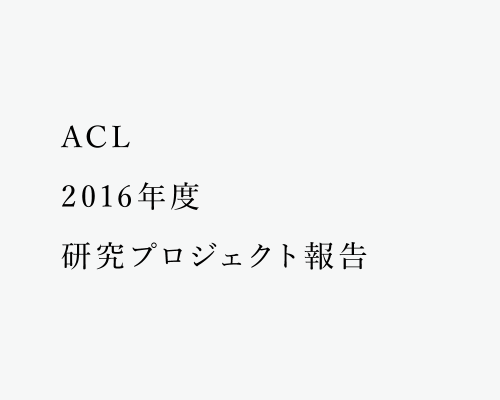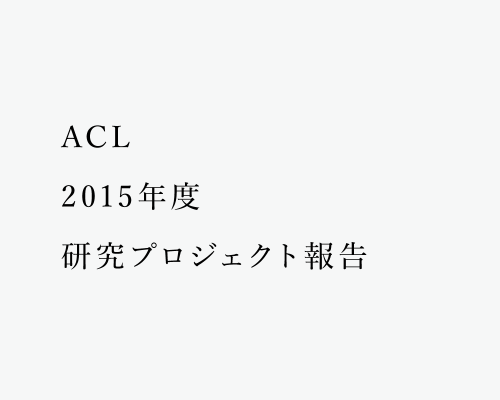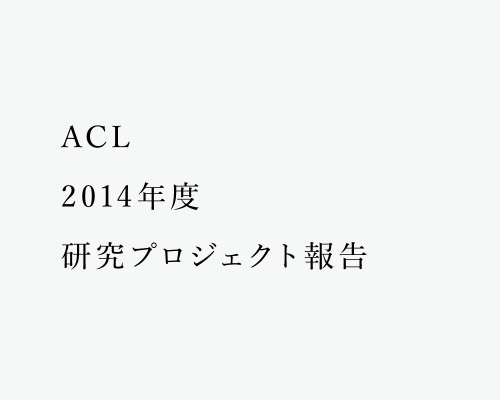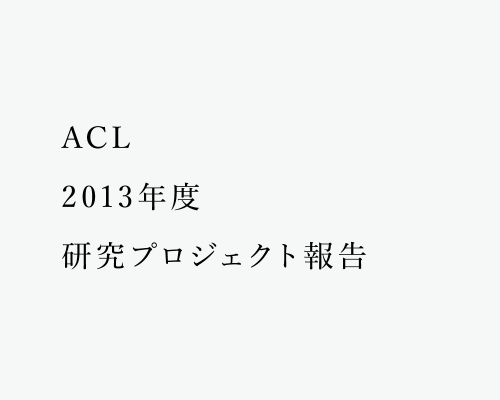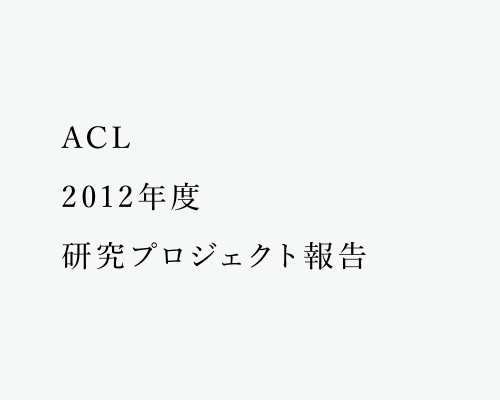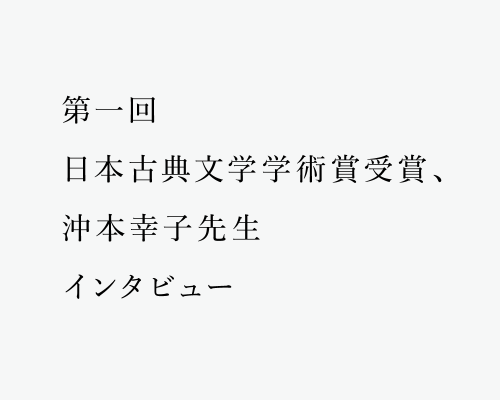- ARTICLE
- 第一回 日本古典文学学術賞受賞、沖本幸子先生インタビュー(1)
- March.01.2021PRINT THIS PAGE
Part 1. 今様への道――沖本幸子×杉浦勢之
杉浦:沖本先生のご著書『今様の時代』は、日本歌謡学会志田延義賞、林屋辰三郎藝能史研究奨励賞、日本古典文学学術賞と、1冊の研究書が3つの学問分野から3賞を受賞、もう1つ隠れた勲章というのが表象文化論学会の学会誌『表象』第1号の書評の記念すべき第1回目に取り上げられるという、これは大変なものが出て来たなあと。それと同時に、今様というものが、後世の学問領域でカバーし切れるようなものではなかったということの証左であったと思います。歌謡学と芸能史学、古典文学・国文学、あるいは表象文化論にかかっている。それぞれの分野から見て非常に大きな仕事であったし、今様がそれらの分野のいわば源泉のところにある、極めて特異な存在であったということをも示したわけですね。
しかし実に雅な本ですね。装丁からしてね、いかにも古典という感じで。
沖本:実は、私は中身に合わせた猥雑な装丁にしてほしいと言い張ったんですが、編集者が譲らなかったんです。でも、いざ出版したら、みなさんから誉めて頂けたのが表紙でしたので、後から編集者に謝ったという(笑)。
杉浦:ああ、そうか(笑)。今様というのは、雅というのとは程遠い世界ですものねえ。なるほど、それでは早速ですが、この雅な本の実は雅とは言えそうにない世界について説明を簡単にして頂けますでしょうか?
沖本:「今様」というのは12世紀の流行歌なんですが、それが古代から中世にかけての過渡期に宮廷社会に入って何を引き起こしたか、ということを追いかけたのがこの本です。当時は、院政が始まり、武士の力も増大して、王権も一種の危機に瀕していましたし、王朝文化も爛熟しきっている。一方で庶民がとても豊かに元気になっている。そうした時代に、少し前までは貴族から「卑俗なもの」としてしか見られていなかった庶民の流行歌が、宮廷の中にも入り込んで、天皇や上皇まで巻き込んで大熱狂を起こしていくわけです。そして、今様が呼び水のようになって社会全体の芸能熱を生み出し、能狂言などたくさんの芸能を創り出していく原動力になったという。そのプロセスを追いながら、なぜ今様がそんなことをなしえたのか、今様の力についても考えようとしたものです。
杉浦:どういったきっかけで沖本先生は今様に興味を持たれたのですか?
沖本:もともとのきっかけは後白河院でした。源平合戦時代の帝王で、日本一の大天狗と言われるような権謀術数家で、非常にずるい人だという言われ方もしますけれど。彼がこの今様に夢中になりまして、帝王なのに庶民の流行歌だったはずの今様の歌詞集と芸論集を20冊も作ったんです。現在はその一部分しか残っていないんですが、その芸論集、『梁塵秘抄口伝集』が私はすごく好きだったんです。
なぜ好きだったかと言うと、今様狂いをしていた後白河院の有様というのがともかくすごい。朝から晩まで寝るのも惜しんで今様をずっと歌い続けるとか、100日とか、1000日とか続けて今様を歌うとか、そういう修行のような形で歌い続けて、喉を壊したことも三度くらいあって、それでも歌わないと気が済まないから歌い続けて血を吐きながらも歌っていくという。なんでここまでしなくちゃいけないのだろうと思うほど今様に入れ込んでいく。
そして、あげくの果てに今様を歌って往生するのだという信仰に達してしまうわけです。当時は、歌のような文学的な言葉は嘘言だから往生の妨げになるという狂言綺語観があった時代でしたし、後白河院自身も仏教に深く帰依していたはずなのに、それも乗り越えちゃって、私は今様を歌って往生するのだと言い張る。論理とか常識とかを飛び越えて、確信として書き記してあるわけですよね。
流行歌だったはずのものに何故そこまでのめり込んで、かつ信仰という形にできちゃうのか。帝王にそこまでさせちゃう今様ってなんだろうと、そういう興味があったんですよね。
杉浦:仏教は大事だけど、「声」がもっと大事というのがすごいですね。しかも江戸時代の国学者のように日本開闢以来の信仰やメンタリティーへ、とはならず、時代の流行歌のほうに抜けてしまう。そこが実に興味深くって、国学のような音声中心主義とも違うところなんですね。あのね、この本を読ませて頂いて、Ⅰ部、Ⅱ部、Ⅲ部という構成になっているじゃないですか。やっぱり、後白河院がメインに来る第Ⅱ部が図抜けてすごい(笑)。今回、この第Ⅱ部を読んで、初めて後白河院という人の体温というかそういったものを感じて、この本は突き抜けてるなって。
沖本:一番怒られるところですけれどね(笑)。
杉浦:僕なんかは後白河院というのは、できたら関わりたくない人だったんですね(笑)。
同時代の人間、政敵の頼朝から「大天狗」と言われる一方で、身内や側近からはこんなわけわからん愚鈍なやつはいないとも言われている。おまけに判官贔屓のお国柄ですから、源義経を籠絡して頼朝との兄弟仲を分断したというので、後白河院というのはとんでもないやつだというのがあって。そこに今様狂いというのが付き纏うわけでしょう。今様という言葉は「ポップ」という意味になるんでしょうが、それ自体よくわからない、何だかとてもいかがわしいものの気がするわけですよ。それから異常なまでの熊野詣という、要するにモノマニアックで、呪術的、薄気味の悪い人だというのがすごくありましたね。
もともと今様は、猿楽ですよね。民衆の芸能だったのだろうと思うんですが、それがなぜ宮廷に入っていったのですか?
沖本:いかがわしいから面白いんですが(笑)。
もっと王権とか宮廷がしっかりしていた時代には、貴族にとって、民衆のものというのは卑しいもので、否定すべきもの、どうでもよいものだったと思います。ところが院政期、王朝文化も最盛期を過ぎて、成熟を通り越して爛熟状態、飽和状態になってしまっている中で、もっと新しい風とか、違うエネルギーが欲しいという風に、意図的にではないだろうけれど宮廷の人々が感じ始める。そんな時、京の町中には富を持つ活発な庶民の世界が出現していて、祭りや芸能も盛んになって祝祭的なエネルギーに満ちあふれていた……。うらやましいというか、ともかく楽しそうなわけですよね。だから、貴族が庶民の祭りをわざわざ見に行ったり、庶民の風俗を詩歌に詠み込んだりして、庶民の文化に興味を持ち始めるんです。そして、それを取り入れる中で硬直した何かを打ち破りたいというような、無意識かもしれないけれどそういう動きにつながっていく。その中で、猿楽と言われるような大衆芸能、道に溢れているいろんな芸能の中の一種に過ぎなかった「今様」のような流行歌が、宮廷の中に入り込んでくる隙間ができてきたのだと思うのですが。
杉浦:それを現代風に文化と言っていいかというのはあるわけですが、もともとは中国だと思うのですが、礼楽思想というのがあって、礼とか楽っていうのが天子というか皇帝の修めるべきことであるという考えがありますよね。恐らく日本の場合、楽については雅楽という形で入ってきているのだと思うのですけど、普通に考えると権力とか政治とか、そういったものとちょっと違うように見えるじゃないですか。ところがそういう危機に際して、文化という言葉があったかどうかは分かりませんが、庶民の文化というものを引き込んでいくことが自分達のエネルギーになる。あるいは、時代と関わって、それを自分達のものにしていくというメンタリティーが、社会科学者にはどうも分かりにくいわけですよ(笑)。
沖本:なるほど……。ただ、近代以前の日本では、政治と文化の関わりはもっと根深いです。権力の側が文化というものの恐ろしさを知っていたというか……。たとえば、白拍子とか専修念仏とかがはやり出すと「亡国の音」という風に言われる。「正統」な音楽、思想からはずれたもの、新しいものの登場にそうした反権力、反体制の臭いを感じ取るんです。あるいは、「ワザウタ」というのがありますが、これは突然わけのわからない歌が流行る、それが実は何かの予兆であるというもので、アニメ「ちびまる子ちゃん」の「おどるポンポコリン」の歌がはやった時に「平成のワザウタ」と言う人がいましたが、流行現象というものに民意や神の意志を見る、そういう感覚は持っていたと思います。
もっとも、院政期の貴族達が政治的に民衆のものを取り入れようとしていたかどうかはわからなくて、少なくとも庶民文化が最初に入って来た時は、もっと自然に入ってきたような気がするんです。政治的意図という以前に、政治や制度に綻びができてきた時代。もはやそうせざるを得なかったというような……。
たとえば、今様より少し前の時代ですが、白河院の娘が「田楽」という簡単な打楽器をはやしながら曲芸をする庶民の芸能に夢中になります。もちろん京で大流行していたからなのですが、白河院最愛の娘でもありましたし、彼女を喜ばせようという気持ちもあってか、その田楽を宮廷の貴族達がものすごく好きになって、その真似事をして、ほとんど裸族のような状態で、彼女や天皇や上皇のところに行って見せたりする。京の町でも内裏の中でも夜な夜な田楽パレードが行われて、それが結局彼女が突然熱病で亡くなるまで続くわけです。ショックの余り白河院は出家してしまうのですが、こういう巻き込まれ方を見ていると、政治的意図というだけではとてもすくい取れないものがあると思うんです。
それから、田楽や今様は古代から中世の過渡期に流行しましたが、時代の過渡期、転換期には必ずものすごく大きな芸能熱が起きるということもあります。幕末で言えば「ええじゃないか」なんかもそうですし、中世から近世への過渡期になると風流踊りの大熱狂というのがあって。
これ、「豊国祭礼図屏風」(徳川美術館蔵)という作品の一部ですが、豊臣秀吉の七回忌なんです。(資料を差し出す)
この時、500もの人が、タケノコをかぶったり、象をかぶったり、ともかくいろんなはちゃめちゃな格好をして踊りにやってきて、そのうち警備の人まで巻き込まれてしまって、結局1000人の群衆が踊り狂ったという……。
田楽といい豊国祭礼の風流踊りといい、本当に熱狂的で。それは、転換期の民衆が何かを感じ取っている。旧制度には納まりきらない身体があって、はっきりとは分からないけれど新しい時代への予感があって、それが集団ヒステリーというか、熱狂的な歌舞の形で出てきてしまうんだと思うのです。
それに体制の側が巻き込まれていく瞬間があるのではないかと思っていて、体制の政治的意図で文化を支配しようとしたというよりも、もっと必然的な形で、体制側が庶民文化に巻き込まれていくというようなことがあったのではないかなと。これはあくまでも私の考えで、もっと政治的意図を見る方もいらっしゃいますけれど……。
杉浦:これは自分の専門がそうだから引きつけてしまうところがあるのかもしれないのですが、そういう意味で時代として体感できるのは60年代末ですね。あの時代はやっぱりいろんな文化とかそういうものがぼこぼこ出てきて、ポップも出てくれば、アヴァンギャルドも出てくる、アングラも出てきますよね。新宿の駅前や歌舞伎町などが、ものすごい「場所」としてのポテンシャルを持つようになって、権力からすれば街に対する抑えが全然きかなくなってしまった。行政が完全に後手、後手に回っていて、明らかに綻びが生じていたんですね。そこを縫うように非日常が立ち現れ、日常とない混ぜになるという、非常に特異な時期だったわけです。もちろん背景に政治的な対立の構図というのがあったわけですが、だからと言って特段新宿という街自体に政治課題があったわけではない。それでも何か起きないかなって人が集まってきたりするんですね。それで本当に何か起きてしまう。「政治的なるもの」を超えるような何か、街自身に集まるパワーのようなものがあったのですね。唐十郎なんかが、今のうち新宿見ておけと言ったような。そういう感じだとするとちょっと分かりやすいかもしれない。
沖本:そうですね。転換期特有の面白さだと思いますが、特に、豊国祭礼が行われた17世紀初頭、中世から近世への過渡期ですが、エネルギーをもてあまして派手な格好をした「かぶき者」なんて、まさにアヴァンギャルドですし、こういう渦の中から出雲の阿国が登場してきたりして、この時代は、とても60年代的なのではないかと思います。
杉浦:ところで、庶民というととかく農民の生活をイメージしてしまいがちですが、都市民の生活というのはそれとはまたちょっと異なっていたと思うのですが、当時どうだったのですか? 猿楽というものを支えていた層というのは都市民だったのでしょう。
沖本:そうですね。猿楽とか今様を享受していたのは都市民です。実際、まさにこの頃から「都市民」というものが成立してきます。たとえば、『病草紙』という絵巻物があるんですが、そこには、札差、金貸しですが、お金持ちになって、太り過ぎて一人では歩けないので両脇を抱えられている肥満の女とか、不眠症の女とか、そういった人たちが描かれている。第一次産業から離れ、肉体労働からも離れた完全な都市民ですよね。
そして、そうした人々が「個」というものを強く意識し始める。一遍などは「一人はいつも一人なりけり」と詠んだりしていて、すごく孤独な、醒めた感覚を持っています。それに都市民が共感して、今様でも、「今」とか「我」とか「我ら」とか歌っていく。そういった近代的な自我のようなものが一方にあり、もう一方に非常に原始的な感覚のリバイバルがある。それは、知的というよりは肉体的、身体的なもので、植物と人間が交感し、交流し、あるいは一遍の踊り念仏のような集団トランスが宗教の中で大きな意味を持ってくるという。非常に土俗的な力が吹き出してくる時代でもあったと思います。
杉浦:なるほどね、「一人はいつも一人なりけり」。それが「今(Now)」と断じ、「我ら(We)」と声を発し始めるというところ、あそこは本当に、今様のもっていたであろう言葉の遂行的な力を感じるところですね。「個」がいわば土俗的な世界の表面に切り出されてくるというか、そういったところで途端に「今」、「我ら」という声がほうはいと沸き上がってくる。しかしそれはかならずしも近代のように身体それ自体を排除して「自己」に向かうものではなかったということなんでしょうね。
沖本:そうですね。宗教も思想も、近代以前の日本では、深く身体性に根ざしたものでしたからね。それはとても大事なポイントだと思います。