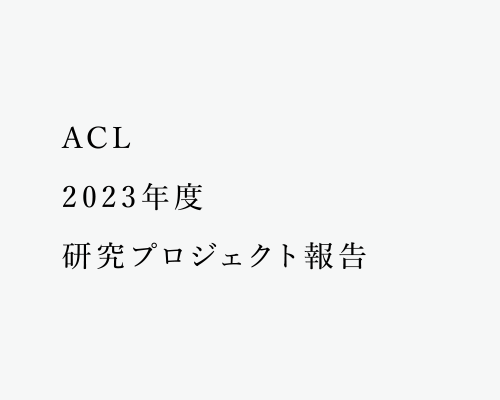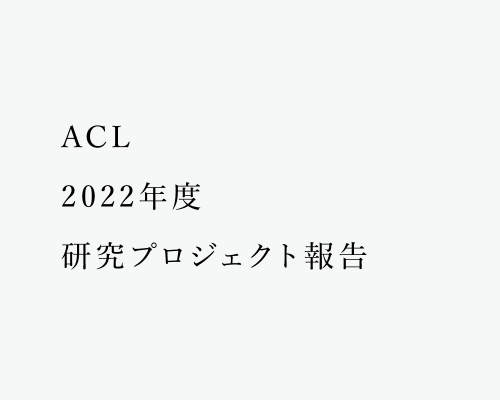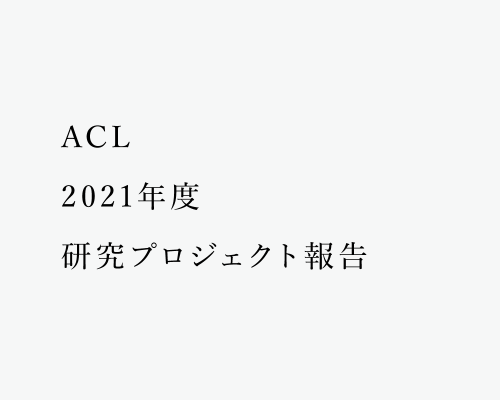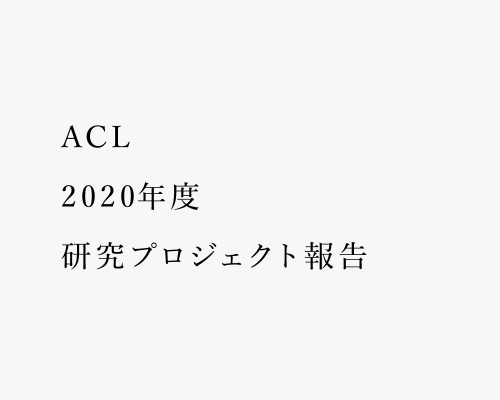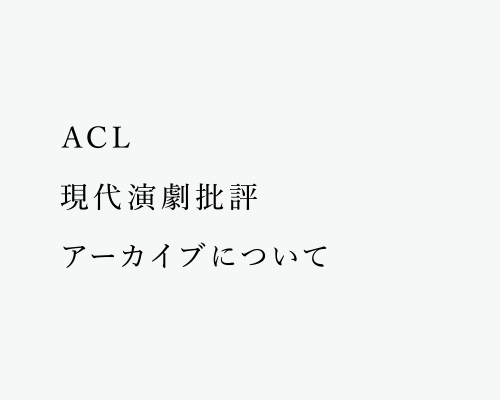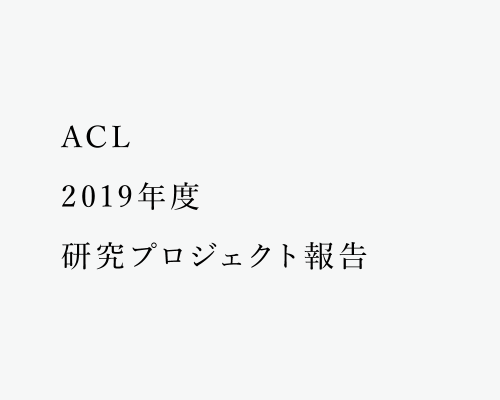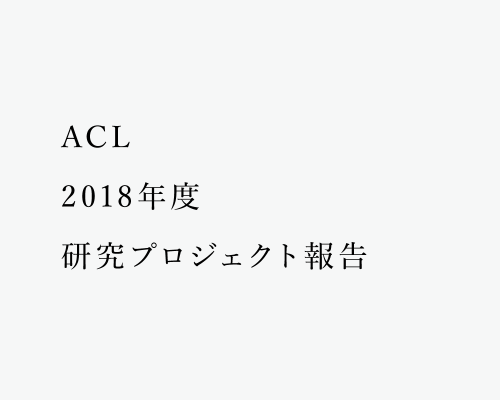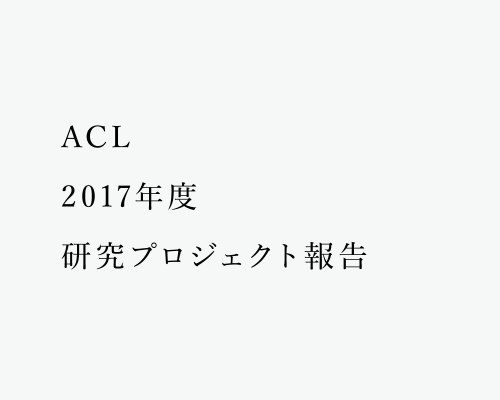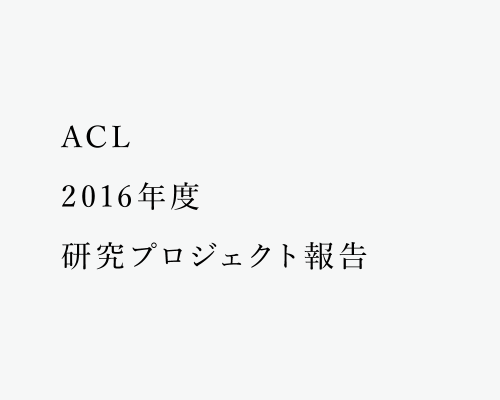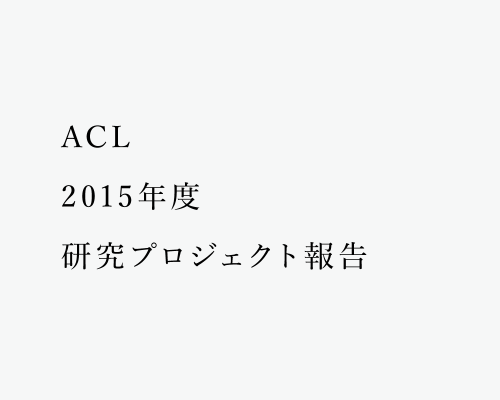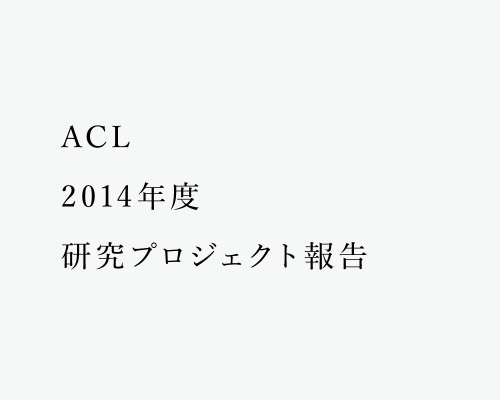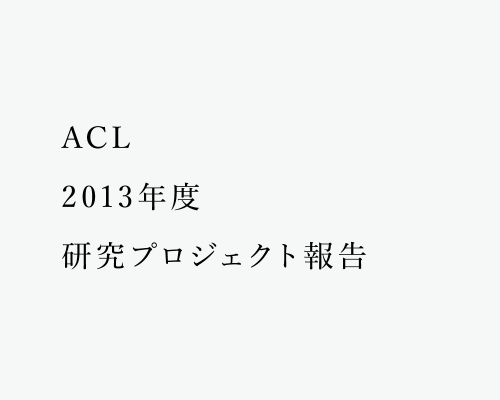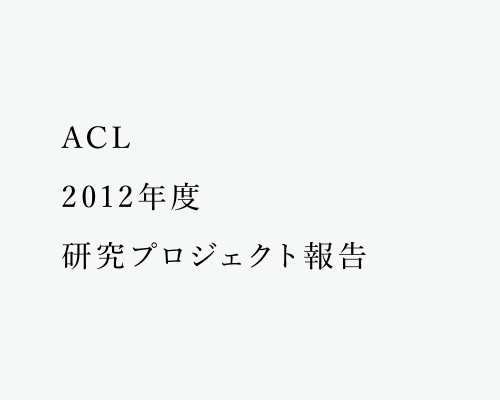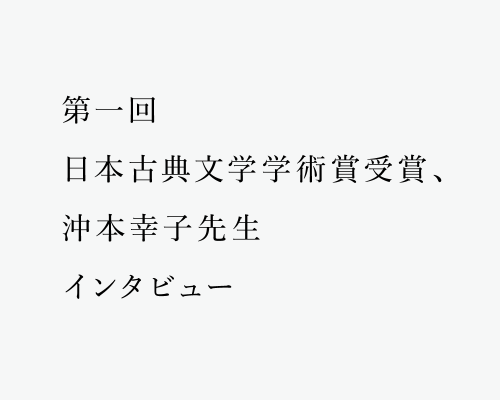- ARTICLE
- 第一回 日本古典文学学術賞受賞、沖本幸子先生インタビュー(2)
- March.01.2021PRINT THIS PAGE
Part 2. 今様の身体性――沖本幸子×杉浦勢之
杉浦:実は僕、先ほど少しお話ししたように、実証的にはちょっとみたいなこと言われたりしたのかもしれないけど、ズバッと聞きたかったのは何と言っても第Ⅱ部なのですよ(笑)。そういう訳で、少し後白河院に絞り込みながらお話しを進めるとして、一番すごいのはやっぱり「声」ですよね。当時は高貴な人は声を出さないとか、女性は基本的に歌わない。これに対して驚いたのは、後白河院が高い声、女性の声をとろうとしたっていう。ある意味では言葉の中身よりも発声そのもの、声質にこだわり続けた。彼の本当の興味は声そのものであったという指摘はすごいなと。
沖本:確かに、あれだけ声にこだわるのは狂気ですよね。ものすごく不安が強かった人なんだと思います。源平の騒乱もありましたし、末法の世でもあり……。非常に混乱し混沌とした時代の中で、どこかに確かなものを求めたい。その確かなものを求める営みの中で、後白河院の特徴は、全部行為になっていくところだと思います。逆に言うと、仏教も教義だけではもう信じられないし、天皇制も物語だけでは支えられない……。
その先が見えないという中で、盛んに造寺造仏をし、平清盛が後白河院に寄進した三十三間堂にしても、横のボリュームといい、一千一体の千手観音像といい、あまりにも過剰なあり方ですよね。あるいは、源平合戦の渦中にもあったはずなのに、33回とか34回とか熊野に赴いて、そのたび毎に帝王が一月近く都を留守にして歩いている。仏教儀礼にしても後白河院の特徴は、お坊さんの説教を聞くという受動的なものではなくて、一緒に御経を読むとか、歌を歌うとか、パフォーマンスとして、行為として全部行っていたところなんです。それは不安の裏返しで、何か自分の実感するものがなければとても信じられないといった感覚があったと思います。
ですから、声への異常な執着を支えていたのは、身体性への渇望のようなものだったと思うんです。言葉の、意味世界の限界を超えていきたいというか……。
そもそも声ってとっても神秘的で、自分の意志で、自分の体の中から出てくるものなのに、どこまで届いていくかわからないじゃないですか。サウンドスケープのマリー・シェーファーによれば、100年ほど前にインドネシアで起こった火山の爆発音は4500キロ離れたところまできこえたそうですから、今から800年前、こんなに音が溢れていなくて、建物もなくて、空気もきれいな世界の中で、音の届く範囲、声の届く範囲って、どれほどだったろうと思いますよね。特に声は、自分の体の中から出てくるのに、意図せぬ所、見えない、知らない世界にも繋がっていってしまうという……。ですから、声というものに対する感覚が今の私たちとは全く違っていて、恐れというか、何か自分を超えた得体のしれない存在であるという感覚を持っていたように思います。
すごく大きな不安感の中で、確かさを求め、身体であり、実感というものにすがっていく。その中で特に突出してこだわったのが声であるというのは、非常にエロティックでもあるし、声が、自分の体内、内側から発せられながらも、未知の世界に繋がっていくものという感覚があったからではないかと思います。だからこそ、自分のものにしたいという。
杉浦:そうか、輸入された教義や文字表記の「日本」化ではどうしようもないところにきてしまっていて、もはや表現された内容が問題なんじゃなく、行為そのもの、あるいは身体の内と外が繋がっている状態、そこに圧倒的な現実感を求めるようになっていたということなんですね。それにしても「高い声」というのがね、フェティッシュであることは間違いないんだけど、男にも女にも自在になり得るという、何か両性具有的な全能感というのか、ホモセクシュアル……いやトランス・ベスティズム(異性装)的なものがあるのかなあ、と思ったんですよ。最近も男性歌手がファルセットや高い声を競ったり、意図的に女性の歌をカバーしたりする傾向がありましたでしょう。その辺はあまり触れられてないのですが。
沖本:日本人の高音志向というのもありますし、簡単に言うのは難しいんですが、中世というのは、ホモセクシャルがものすごく広く蔓延していましたし、貴族社会の美の基準は一貫して女性美だったということもあると思います。特に、男性が女性性を持つことに意味があって、だから、「高い声」が理想であるというのも、女性美へのあこがれというのがベースにあったと思います。光源氏の美しさも女性的なものとして描かれていますし、稚児という少年は、高僧のセックスの相手でもあったんですが、彼等には宮廷女房風の装いや教養が求められ、髪型から眉の描き方、身のこなしまで女性的に作り上げられていました。こういうところには、確かに両性具有的な全能感への指向があるのかもしれませんね。
杉浦:ああ、ホモセクシャルや異性装って当たり前だったということなんですね。それであえて触れるほどのこともなかったということですか。いやあ、それは……草食系イケメン男子どころの話ではないですね(笑)。
ところで第Ⅱ部の終わりの辺りから急激に、後白河院によって今様がどんどん取り込まれていって、文化的に爛熟するというふうになるわけですね。むしろそのために今様の世界が公認的なものになってしまい、いわば正統化され、硬直化していくという指摘がなされています。一回性の声の質にこだわりながら、それを『梁塵秘抄』として網羅的に書きとめていくことにより、文字に回収していこうという、後白河院の今様に対する真逆のスタンスを指摘されておられます。家元的正系の発生などを考えますと、それ自体大変興味深い指摘なんですけれど、何よりそこからこぼれるものが、次の芸能を満たしていくという。そこにエネルギーが移っていき、途端にばっとリズムが出てくるんだという、この移行のところが、無茶苦茶面白いですよね。
沖本:そうなんですよ。歌って歌って歌い尽くして、そのエネルギーをそのまま追いかけていったら、いつのまにかリズムの時代になってきて……。王朝美というのは、ゆったりしてますからメロディ中心で、リズムが好まれるような文化では決してなかったと思うのですが、あれだけ声の世界を味わい尽くしてしまうと、もう、次は踊るしかない(笑)。
そんな時、鼓のリズムに合わせた「ノル」身体というものが出てきます。今でもノリが良いとか悪いとか言いますが、「ノリ」という言葉自体、能の用語から生まれたもので、まさに、そうした身体がこの頃に誕生するんです。
そして、もう一つは武士が力を持ってくるということ。非常にリアルな問題として肉体の力が大きな意味を持ってくるし、宮廷の下級武士が芸能者として活躍し、寺院でも下級僧侶は武士であり芸能者でもあって、武士と芸能者とが重なりあってくる。そういう中で、武士のような身体的能力の高い人たちがノル身体を面白くしていったのだと思います。
時代の鼓動というものが武士の時代を生み出し、リズムの時代を生み出していく。鼓のプロが生まれ、鍛えられた身体が出てきて、その鍛えられた身体が律動的なリズムにのって舞っていく。それは、マッチョな身体、男性芸能の真骨頂でもあって、だからこそ、猿楽能が男性芸能者たちによって完成されていったのだと思うんです。これは、雅楽のゆったりしたメロディに合わせて流れるように舞う舞楽には全くなかった面白さで、この楽しさに中世の人たちは夢中になっていく。だから、人が集まればリズムにのって即興舞をする、それを当時は「乱舞」と呼んでいたんですが、まさに「乱舞」の時代、踊り狂う時代になっていくのでしょうね。
杉浦:なるほどね。沖本先生歌わないけど踊りますからね(笑)。対象とする世界の身体性と、書いている著者の身体が重なり合うというか、沖本先生は第Ⅰ部のところではまだ端正に正座しておられる感じなんだけど、第Ⅱ部の後白河院でうーんと溜めに溜めていて、最後の方でポンポンポンと芸能に繋ぎながら第Ⅲ部に移っていって、乱舞、乱拍子のところで、バーっと解放されるといった感じですよね。
沖本:それは私自身の解放でもあったということですかね(笑)。
杉浦:そうそう(笑)。あれは見事だなーと思ってね。いい学術書の対象と著者と章構成の関係ってそういうものなんで。もっとも素人があんまり褒めちゃうと、沖本先生そんなんじゃないよと、後でいじめられちゃうかもしれないけどね(笑)。
沖本:そうそう、もっといい加減だとみんな知っています(笑)。
でも私自身、今様で終わってしまったら本は書けなかったと思うのです。今様がこれで滅びて終わりっていうのでは悲しすぎて……。
実は、本にまとめる何年も前のことですが、表象文化論の研究会の席で、この時代の「過剰な身体」の話をしたときに、身体論を専門にされている石光泰夫先生に、過剰な身体というものは次の時代に引き継がれたり、過剰な部分が何か新しい芸能を生み出したりすると思うけれど、それはどうなのか、と聞かれたことがあったのです。私はその時とてもはっとして、そうだ今様は滅びるかもしれないけれど、このエネルギー、この芸能熱、帝王も貴族も僧侶も庶民も踊り出さんばかりの熱気に溢れていて、絶対どこかで新しい芸能に繋がるっていう確信みたいなものが生まれました。そうして追いかけている内に、ある時代から、歌の時代でなくて「乱舞」の時代になっていくのが見えてきて、これは間違いなく繋がっているだろうとわかってきて。だから、私も今様と心中せずに済んだというか(笑)、本を書くエネルギーもでてきたのだと思います。
杉浦:僕は酒井直樹さんの『過去の声』という本を読んでいて、18世紀の言説空間が取り上げられているんですが、その中に「舞踏術の政治」などという章があったりしましてね。いささかスタティックですが見事な分析で、子安宣邦さんなんかの近世思想史の議論も踏まえながら読んでいたときに、ピっと繋がったのですよ、沖本先生の後白河院。今にも踊り狂おうとしている(笑)。だから後白河院という人はぎりぎり政治的な人でもあり、ある意味では大変孤立した人でもあり、どうしていいか全然わからなかった人でもあるって考えると、狡猾にして大胆かつ愚か者っていうのは何となく見えたかなと。
沖本:非常に動物的勘の強い人だったんだと思います。頭で考えて理屈で動いている人じゃないから、脈絡がないように見えるのではないかと。
杉浦:あまりにも動物的ですね。声の質にまで自分を還元出来てしまう。傍で何とか意味を読み込もうとしたら、こいつ大馬鹿か、と(笑)。一方、遠くで結果だけ見ている奴は、こいつはとんでもない食わせもんだ、と(笑)。
沖本:ははは。彼は末っ子ですから、帝王教育も受けていなくて気ままに育っているんですよね。そういう事もあるし、本人の資質と言うこともあったと思います。それが、ああいう混乱した時代の中で、時代に翻弄され、時代を翻弄しながら生きていくことになってしまったという……。
杉浦:偶然が重なって中継ぎで天皇になってしまった人ですからね。そういう意味では、沖本先生のお仕事、最初に特異な世界と紹介したわけですが、実は文化の王道をやられているのかもしれないですね。ご本を読んでいて、今様というのは、列島社会の深層が一瞬表層に浮き上がったという意味での「特異点」だったんじゃないかという気がしたんですよ。列島文化というのは圧倒的に大陸文化の影響圏にあったわけですが、一方で地下水脈みたいなものがあって、それをなぞることで表向き王道が形づくられている。まったく固有なものとして文化があったわけでないのと同時に、大陸の影響だけで文化が成り立っているのでもない。その鬩ぎあいが道を創っているみたいな。そこで下手に王道を外してしまうと、あっという間に水源と切れて枯渇してしまう、そういう複雑さを感じるんですね。それこそ、今様三昧の後白河がなぜ熊野まで行かなければならなかったのかという、元々自然信仰の聖地ではあったわけでしょうが、そういう事ばかりでもないでしょう。京都に繋がる地下の水脈が確実にあったんだと思うのですね。そういうダイナミクスがあって、帝王たりと言えど、それを無視することはできない。そういうのが、動物的勘でよくわかっていた人だっただろうと。
沖本:院政期というか、転換期、過渡期の面白さですよね。地下にあるものまで吹き出してきて、普段は見えないものまで露呈してしまう、表面化してしまう、そういうところが転換期研究の醍醐味です。後白河院も、ああいう時代だからこそ出てきた人だと思いますしね。
杉浦:僕ね、もう一つ実はお聞きしようと思っていたことがあって、それは近代のことだったんですよ。それは、「今様の時代」を通してみたときに、近代日本に入るところで、表記や語りとの関係で「声」というものがどのような運命をたどったとお考えなのかなということなんですが、今日のところはそこまでいく余裕がないと思うので、ちょっと宿題にしておこうと思うのですが、しかしその前提として、どうしてもお話しいただきたいなと思うのが、列島社会の書き文字の宿命ということについてなんです。簡単に言うと日本の表記言語といったって、最初は文章としたら中国語を読んでいたわけじゃないですか。それで、ようやっと仮名を作り、音声文字を獲得して、いわば自分の心のリズムや情意を文字として表現できるようになった。おそらく、それはとても歓喜に満ちた体験であったろうし、エロティックな体感を伴うものだったと想像するんです。そういう体験が国風文化にあって、そしてそれが洗練され尽くし、行き詰まった先に、心の残余の部分というか、ぎりぎりの身体感覚の部分が堪らず本当の肉声を出し始めたっていう流れはすごい話だなあと思うのですよね。
沖本:そうですよね。仮名文字ができても、やっぱり日本では長らく漢文こそ正式という感じでしたから、そういう教養主義をかなぐり捨てなきゃならないような、本当にせっぱ詰まったときに、声の問題が出てくるというか……。
ご指摘の通り、近代にも同じことが起きていますよね。西洋文化の流入と伝統文化排斥運動の中で、洋楽が入ってきて発声法も音階も変わって、詩歌の分野でも「和歌」から脱した「新体詩」を目指そうとした。これは今取り組んでいるテーマでもあるのですが、新体詩運動の際に今様が称揚されるんです。「今様は平安時代の新体詩だ!」「新体詩は現代の今様だ!」という風に言われて、唱歌運動などとも関わりながらブームになるというようなことがありました。
そうした時代から100年以上たって、西洋文化もずいぶん日本に定着してきて、こなされてきて、ここ20年ほどでしょうか、これは世界的な動向、思想的潮流でもあるけれども、日本文化の中でも身体や声のことがずいぶん問題にされるようになりました。ここであまり内向的になってはいけないけれど、日本人の身体性の回復というか、そういう無意識の働きも、近年の身体や声の問題への注視を支えているように思います。
杉浦:読んでいて、同じような経験を、日本人は近代に入ったところでもう一回受け止めたんじゃないかなという気がしたんです。最近も、ロックのリズムにどうやって日本語を乗せるのかというところでそういう部分を味わったんじゃないでしょうかね。そういう意味で、声の中身より声質そのものにこだわり、一方でそれを網羅的に収集して表記することに異常なエネルギーを割くという、沖本先生の後白河院の「声」という問題構成の射程というのは、実は相当広い、江戸の国学に先行し、現代のポスト・ポストモダンにも通じるものがあるのじゃないかと。これはむろんほめ言葉なんですが、ご本人はそういう見通しというか、図式的整理におよそ興味を持っておられない節があるんだけど(笑)。先ほど地下水脈との関連で列島文化の王道を扱われているのかもしれないと申し上げたのもそういうことなんです。
沖本:「文化の王道」かどうかはわからないですが、ただ一つ言えることは、自分自身の「予感」と「違和感」に正直に歩いてきたということでしょうか。最初はいつも曖昧模糊としていてよくわからないのですが、何か「予感」があるから、その対象に飛び込んでいくことができる。あるいは、自分の中にある「違和感」を丁寧にひもといていくときに、その根っこにあるものがちらりと姿を見せてくれるようなことがあったりして。現代に生きている私の予感や違和感というのは、私が浮世離れをしていても、やはりどこかで現代と深く関わってくる部分もあって、だから、結果的に色々なことにつながって見える……というようなことはあるのかもしれません。私自身は、現代というものに何か大きな違和感があって、その違和感の正体を明らかにするために、それをよりヴィヴィッドに感じるために、歴史をひもといているという……。
杉浦:「予感」と「違和感」というのはいい表現ですね。
ところがここ数年の学生は違和感を持っちゃダメ。予測できること以上の予感なんか持っちゃダメ、と本気で思っているのですよ。就職のためにはね。しかし悩むこと、考えることを今やらなかったら一体どうするのだろうと思いますよ。
沖本:えー、私なんて、ほとんど予感と勘違いで生きてきましたけどね(笑)。
杉浦:違和感じゃなくて勘違い……(笑)。
いやー、沖本先生はそれでいいんじゃないかなあ、楽天的で明るくて、エネルギーいっぱいでね、「勘違い」なんておっしゃりながら、きっちり的を射抜いていたりして。そういうところが魅力なわけですから。